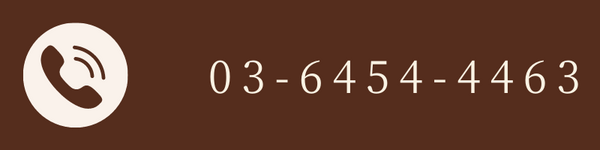こんな症状ありませんか?
✓ 座っていると腰が重くなる
✓ 姿勢が崩れて、頭が前に出てしまう
✓ 首や肩がいつも緊張している気がする
これらの不調、実は“骨盤の後傾”が関係しているかもしれません。
骨盤の位置が変わることで、身体の運動連鎖が断ち切られ、首や腰に余計な負担がかかってしまうのです。
この記事では、骨盤の傾きが全身に与える影響と、K.G.Laboでの改善アプローチをわかりやすく解説します。
骨盤後傾が引き起こす運動連鎖の断絶
骨盤が後ろに傾くと、背骨の自然なカーブが崩れ、股関節や胸椎の連動がうまく働かなくなります。
その結果、肩甲骨の動きが制限され、頭の位置が前方にずれ、顎が上がるような姿勢に。
この状態では、首や腰が代償的に動くことになり、負担が集中します。
つまり、骨盤の後傾は「動きの起点」を失わせ、身体の各部位が本来の役割を果たせなくなるのです。
K.G.Laboでの整体アプローチ
K.G.Laboでは、骨盤の位置を整えることで、運動連鎖を回復させる施術を行っています。
✓ 骨盤・股関節の可動域を広げるアプローチ
✓ 胸椎の柔軟性を引き出す調整
✓ 頭部の位置を整える感覚教育
これにより、首や腰の負担が軽減され、自然な姿勢が取り戻されていきます。
施術だけでなく、日常動作の中で「動きの起点」を再教育することも重視しています。
正しい姿勢になるためのK.G.Labo流 9つの法則
① 骨盤は「軽く前傾」させる
└ いわゆる「はけ前」の状態。
恥骨とへそのラインがほんの少し斜めになるイメージ。
② 足の向きと膝の向きを合わせる
└ 足先と膝のお皿が同じ方向を向くように意識。
③ 足の中指を正面に向ける
└ 中指が正面を向くことで、股関節〜膝〜足首の軸が整う。
④ 膝のお皿も同じ方向に向ける
└ 足指と膝の向きが一致することで、下半身の安定性が高まる。
⑤ 胸を開くために肘の位置を意識する
└ 肘を後ろに引くことで、肩が上がらず、鎖骨が左右に広がる感覚に。
⑥ 肘は洋服の背中側(繊維の後ろ)にあるように意識する
└ 肘が縫い目より後ろにあることで、肩甲骨が自然に動きやすくなる。
⑦ 整える順番は「下から」
└ 足元→骨盤→胸→首の順で整えると、全身が自然に連動する。
⑧ 骨盤や足元から整える
└ 姿勢の起点は下半身。まずは土台を安定させることが大切。
⑨ 最後に顎を引いて頭の位置を決める
└ 顎を軽く引き、頭頂部が天井から糸で引かれているような感覚で首を長く保つ。
日常でできる予防と習慣化
✓ 長時間の座位では、骨盤を立てる意識を持つ
✓ 顎を引き、頭の位置を真上に保つ習慣
✓ 胸を軽く開くような姿勢を意識する
✓ 動作の起点を「股関節」に置くようにする
K.G.Laboでは、こうした習慣づくりもサポートしています。
「なんとなく姿勢が崩れている気がする」「首や腰が疲れやすい」そんな方は、まずは日常の姿勢から見直してみましょう。
まとめ
骨盤の後傾は、首や腰の不調の根本原因になることがあります。
姿勢の崩れが気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。
【初回5,980円で試してみる】